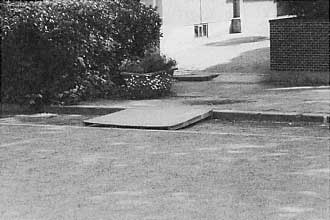INDEX ● Image appending >>image list
● メーリングリストの「使用上の注意」と可能性 粂 和彦 >>INDEX
|
メーリングリストの「使用上の注意」と可能性
〜分解・衰退・荒れを防ぐために〜
●情報とコミュニケーションの変遷
人間は、言葉により、内容の濃いコミュニケーションができるようになりました。数千年前に、文字を発明し、これは記録の役割を果たすと同時に、手紙となって、離れた場所にいる人との、意思疎通を可能にしました。
平安時代の書簡のやりとりは、今、読んでも素敵ですよね。
また、産業革命の頃の印刷の発明で情報の大量増幅が可能となります。
そして、インターネット!
一般に普及してからは、せいぜい10年しか経たない技術ですが、そのもたらした影響と、広がりの速度は、前例がないでしょう。
●電子メールは文字文化ではない!?
ネットを介した情報交換のツールを、別表にまとめますが、電子メール(以下、メール)の最大の特徴は、メールが、話し言葉に近くて書き言葉ではない、という点だと思います。
書き言葉のことです。メールが登場する前には、この二つ、話し言葉と書き言葉とにはある程度、しっかりした区別がありました。
紙に書かれる手紙には、書き言葉を使います。普段、電話などでは、気安く話ができる相手でも、手紙では、「拝啓時下益々ご健勝のこととお慶び申し上げます・・・敬具」なんてつけるのが、一般的です。
一方通行で、時差のあるコミュニケーションなので、書いた瞬間と、読む時では、時間差があることを意識して書かれるのが普通です。
一方、電話で話されるのは当然話し言葉ですが、その特徴は、絶対的な同時性と、言葉に感情がこめられることです。
では、メールは、どうでしょうか?
メールは、ある意味で手紙以上に、書き言葉です。
なぜなら、手書きの手紙なら、文字の感じ(丁寧に書いたり、くだけた丸文字で書いたり)や、便箋の質(暖かい絵のついた紙と、無機質な事務用の紙の違いなど)で、ある程度の気持ちを込めることができます。
涙や鼻水のシミもつくかもです(笑)。
でも、現在のメールの多くは、単なる文字の羅列です。
実際、知らない人に初めてメールを出す時には、ほとんど手紙と同じような文体を使うこともあります。
また、メールを使い慣れない人は、文字の手紙と同じような書き方をいつまでもします。
しかし、最近の多くの人にとって、メールは話し言葉的に機能しています。
とはいっても、メールは単なる文字の羅列で、そこには、なかなか文字情報以上のものはありません。そこで、顔文字や、くだけた言葉を使って、話し言葉的にするわけです。
ネットでも、チャットは、電話に近いですし、手紙でも、ハリーポッターに出てくる、「どなりつける手紙は、話し言葉化の究極です。
この文章も、メーリングリストに、あいさつ文を書く時の「のり」で書いているので、「固い書き言葉的な文」を読み慣れた方には、とっても違和感があるはずです。
でも、それなりに柔らかくて、読みやすくありませんか?
●メーリングリストを使ったコミュニケーション
メーリングリストは、その仕組みの上でも、従来には全くなかったコミュニケーションツールです。
1.最大の特徴は、「面識がない多数の相手」と、いきなり、直接の対話ができることです。
逆に言えば、顔の見えない、何を考えているかわからない、多くの人の前で、いきなり挨拶・スピーチをするようなものです。
情報の受け手側の匿名性ともいえます。
2.受け手側だけでなく、情報を発信する側にも、匿名性があります。
たとえ、実名での署名があっても、面識がなければ、年齢もバックグラウンドもわからないので、名前にはほとんど意味がなく、匿名と考えられます。
肩書きなども、一定の判断材料を提供するに過ぎません。
3.情報が発信されて、すぐ届くこと(即時性)、無料で、紙も切手も不要で、簡便に書けること。
話し言葉的な気安さと、書きやすさ。
4.面識がない相手の場合、字体、材料などの情報がなく、表情のない文字の羅列なので、個々のメールに個性が乏しくなります(没個性、または脱個性性)。
そして、誰からのメールも、どのような内容のメールも、同じ外見で届きます。
例えば、従来のメディアなら、大新聞の記事と、週刊誌の記事、書籍としての文章などには、重さに大きな差がありますし、情報の発信は、それなりに知識や経験がある人からされることが多かったものが、メールでは、そのような差別化や、重さの差がありません。
平等とも言えますが、極端に偏った意見も、同じ重さを持つように感じられます。
5.参加者の反響が感じられない、のも大きな特徴です。
ある意見に共感する人が、参加者の中に多いのか、少ないのか、自分のコメントが、どのように受け入れられているのか、体感できないので、つい書きすぎたり、疑心暗鬼になったりすることもあります。
●異なる意見と立場の共有
さて、このような特徴のあるメーリングリストですが、せっかく作ったメーリングリストが、参加者内の対立で、分解したり衰退してしまった経験をした人も多いと思います。
面識がない人間同士が、インターネットだけを介したネットワークを作って、そこから何かを生み出す、つまり「ネットでネットする」のは無理だ、という意見も聞きます。
しかし、ぼくは、限界と注意する点を知れば、建設的な情報交換に基づく、ネットワーク構築にネットが利用できると考えます。
最大のポイントは、メーリングリストは情報の共有の場であり、知識・情報の格差を無くす場ではあっても、意見の差を無くすための場ではないことです。
意見の差には、基礎となる情報や経験が異なるために出てくるものと、思想・嗜好・イデオロギー的なものがあります。
前者は、情報を共有すれば、無くなることもありますが、後者は、基本的には、ネットに限らず、どのような手段でも簡単には埋まらない差です。
上手な情報共有経験をたくさん分かち合えば、メーリングリストのメンバーにとって、そのメーリングリストは有意義になります。
しかし、お互いに意見そのものの差を即時性・簡便性のあるメーリングリストで、無くそうと議論するのは、当事者のみならず、メーリングリストの全メンバーにとって徒労です。
直接会って、議論している時には、その議論の中で、どこまでが妥協できる点なのか、比較的、見分け易いし、考える時間と話す時間が限られているので、譲りあい易い面があります。
ところが、メーリングリストでは、時間が無制限にあり、いつまでも反論ができます。
ただし、この二つの差の間に、いつも最初から、簡単に線が引けるわけではありませんし、ある部分までは、お互いに意見が変わって、近づけるということもよくあります。それを、意見交換の中で見つけることができるのも、メーリングリストの醍醐味でもあります。
●今、再び、ネチケット
では、どうすれば、無駄なメール交換や、場が荒れる対立をさけることができるか・・・ここでは、具体的な方法を提案します。
ただし、これはルール化するという性質のものではなく、管理・運営者、または場合によっては、積極的な参加者の一人として心がけて、それた場合、介入する、という意味です。
1.質問・反論の回数を制限する:
質問・反論は、せいぜい2回までです。
たとえば、3回以上、「それは、なぜか?」という質問するのは、禁忌(やってはいけないこと)だと思います。
普段から、よく考えている人でも、自分の考えの根拠を、3段階以上、答えられることは少ないものです。
自分の意見を説明しながら、相手の意見の根拠を聞いたり、相手の意見の不備を指摘するのは、3回を限度とするのが、無難です。
もちろん、建設的に意見交換が続いている時には、何度でも構いません。
2.反論は一晩寝かせる:
メールの特徴は、即時性ですが、それが逆効果になるわけですから、それを避けるために、わざとローテクを使います。
実際、一晩、待つと、考えていることが大きく、変化することもあります。
3.部分的な反論は避ける。
相手のメールの部分部分を引用して、相手の論点のいくつかに個別に反論・コメントすることは、多くの場合、揚げ足取りにもなります。
もちろんケースバイケースで、部分否定・部分コメントが有効な場合もあります。
4.異なる意見は、空中に投げる。
部分的な反論を避けるため、ある意見に対するダイレクトな反論という形ではなく、別の意見として、ひとつのまとまった形で新規にコメントを投稿する方が、効率的な意見共有ができます。
5.頭を冷やす。
ネット上では、全ての参加者が全く等価に感じられてしまいます。
しかし、現実には、一定のディベートが成されていれば、たとえ、その直接の相手を論破・説得できなくても、他のサイレントなメンバーは、きちんと評価するはずです。
相手を負かす必要はありません。
6.許容的になる。
どのような状況でも、極論が飛び出すことがありますが、それらの極論も完全に打破したり、排除する必要など、普通は全くありません。
その人自身を説得するのが、メーリングリストの目的ではない以上、極論には、それが極論であることを1回だけ指摘しておけば、充分です。
7.これはメールに限りませんが、論点ではなく、相手の人格批判や、別の点での反論・コメントはしない。
日本人は、ディベートに慣れていないせいなのか、政治家同士の足の引っ張り合いのことを、ディベートだと勘違いしているせいか、議論の内容から離れてしまうことが、非常に多いようです
8.そして、話し言葉なのか、書き言葉なのか、常に意識することです。
ネットになれた人間が増えれば変わっていくでしょうが、今のところ、まだまだ、メールに対するイメージが、人により大きく異なり、書き言葉的にとらえている人にとって、話し言葉的に書かれたメールは、大変侮辱的に感じることもあるわけです。
以上、いまさらと思われた方もいるかもしれませんが、ネットを上手に使ってネットして欲しいと願っての書き下ろしです。ご了承下さい。
粂 和彦さん(熊本大学准教授)の文章の要約です
全文はhttp://k-net.org/opinions/に掲載 2004.12.
原題は「ネットでネットする 〜インターネット・コミュニケーションを、市民のボランティア活動のネットワークに役立てる」
|
● 1. エレベーター、エスカレーター、階段 月刊「浄土」 2003.6. >>INDEX
 利用者からすると、どれが一番優先されるのだろうか。 それぞれ文明の利器だからといってしまえばそれまでだが、高低差を克服する道具として機能は確かに違う。
ちなみに3つからイメージされるものを考えてみた。 筆者にとってエレベーターとエスカレーターは百貨店、階段は学校である。 いずれもインパクトのあった初体験の場所だ。
これもきっと一人一人違うはずだが、利用者からすれぱ日常的に利用するところにあってほしいのは、一番便利(高価)なもの。
サービス側から後回しにしたいものが、やはり高価(便利)なものだ。なんとも大きな意識の違いを感じる。
こう考えると、利用者の一人として、どこにでもあってほしいと願うのはエレベーターかエスカレーターに決っている。 こんな自然な発想が何事も大切だろう。 この視点はどこでも通用する考え方だと思う。
ところが、バリアフリー(垣根をなくす)的発想から見ても実情はお寒い。 利用者感覚欠如なのだ。
ともかくお年寄りや車いすや乳母車の使いやすさよりは、サーピス側の論理が優先している。
だから、当然エレベーター、エスカレーターは最後の最後になる。 元気なときにしか便利と感じない階段が優先されるのである。 これで何とかやり過ごせないかと言い訳を考える。情けない話だ。
ところが欧州の駅に行くと、3つ全部がそろっているのに目を奪われた。
当地の関係者は、そうしないといけないと思っているふしがある。 だから、一生懸命。 それにカッコいいガラスで透けたエレベーターも当たり前なのである。 とにかくうらやましい限りだ。
できるだけ早い時期に、日本でもエレベーターと階段くらいは、どこに行っても一緒にそろえるのが当たり前になってもらいたいものだ。
文:白木 力 写真:丸山 力 |
● 2.選挙と投票 月刊「浄土」 2003.7/8. >>INDEX
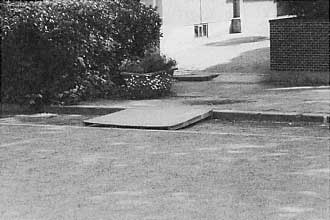 阪神淡路大震災で国内がゆれたのは、1995年、多くの被災者が出た。 あのときに気になったのが、避難所の状況だった。 送られてくるテレビの画像に釘付けになりながら見守ったものだ。 次第に現地の状況がわかるにしたがって、その悲惨な状況が明らかになった。 車いすの人やお年寄りにとってトイレを始め、その環境は過酷を極めた。
時間が経つと忘れてしまうが、一番の避難所になった学校の整備は、まだまだ現在も遅れている。
多くの地域で緊急時の避難所は、小学校、中学校等の公的な施設だ。 このような緊急時に、いつも犠牲になるのがお年寄りや障害者である。
その犠牲の程もマスコミなどでは伝わってこない。 バリアフリー化されていれば防げるケースも多いが、同じようなことが現状でも懸念される。早急な点検が必要だ。
さらに学校などは選挙のときに、投票所として使われる。 だから、なおさら気にかかる。 投票所のバリアフリー化については、多くの地域でも同様にかなり遅れている。 投票所は、学校や市民センター、お寺などだったりする。
簡易な手作りのスロープで済ませたり(写真参照)、人的な力で車いすを抱え上げたり対応は、まだまだ場当たり的だ。 投票所自体が、多くの自治体で選挙管理委員会の管轄でない点も問題を複雑にしている。
教育委員会だったり、市民局だったり、宗教団体だったりと管理者は場所によって違う。 改善はその管理者が責任を持つ、選挙が来るたびに、またシツコク改善を呼びかけたい。
地域をそして国を変えるためには、選挙で一票を投じることが一番の近道だ。 選挙権の行使はことさらに重たい。 各地域の選挙管理委員会はもっと強く、その責任を受け止めなければならない。
ハードにもソフトにも、そろそろメスを入れて欲しいものだ。
文:白木 力
いつも投票所になるこの小学校では、会場の体育館の入ロにベニヤで作られた作りの悪いスロープを見かける。 少しの段差が気になっている
写真:丸山 力
|
● 3.おもて と うら 月刊「浄土」 2003.10. >>INDEX
 何事にも表(おもて)と裏(うら)がある。
一般的に表と裏は全く違ったもののはずだ。 20年位前までは、レコードもドーナツ盤と言ってA面とB面があった。 もちろんA面がメジャー、B面がサブだった。最近これはなくなった。 今の音楽はほとんどがCD(コンパクトディスク)だからA面B面はない。 そりゃ当たり前、ここまではジョークだ。
何でもそうだが、主流があるから反主流があったりする。 しかしこれでは対立しか生まれない。
実は、裏技にこそ際めつけがあり、生きる糧がある。 表技は誰しも持っている。 それではつまらない、だから裏技はないか奔走する。 こどもたちが夢中になる。 コンピュータゲームなどいい例だ。
今の時代、裏も表もなくなったと言ったほうが的確かもしれない。
昔は、裏は本当に裏家業で死ぬまで報われなかった。 しかし最近は、むしろ裏技にこそスポットが当てられている。もはや表とか裏と言う差別感は無くなった。
表の妙味、裏の極意。 知れば知るほどにバリアフリーだ。境目はない。
今の時代は、個性を本格的に生み出せる、まともな時代になった。
谷崎潤一郎が記した「陰翳礼賛」いかにも日本的だが、(陰)裏の世界の良さをことさら引き出している。 表とか裏とか言う言葉にこだわっている限り世界は拡がらない。
表しか知らない人は人生の半分しか楽しめない。 表にも裏にも真理があるからだ。
ものの見方次第で楽しみは、2倍にも3倍にもなる。 確かに裏という表現がよくない。 競争原理を働かせることで質をあげるという幻想があるが、だから白黒をつけたいのだ。
勝者の論理には惑わされないようにしたい。 人生は一度。 バリアフリーを見極める力が必要だ。
文:白木 力 写真:丸山 力 |
● 4.玄関 月刊「浄土」 2003.11. >>INDEX
 玄妙なる関門。 玄関の語源はここにある。 禅宗の言葉を起源とすると聞いた覚えがある。 何とも堅っくるしい表現だ。 語源まで堅っくるしい。
実は、江戸の時代にさかのぼると、この玄関にも表玄関・裏玄関があった。 英語では、エントランスと表現されることがあるが、日本の玄関とは根本的には異なる。 「玄関」には単なる入り口というよりは、外界から一新して帰還してくる場所という意味が盛り込まれている。 生きていくときの境界線という意味からすれば、かなり大切な場所である。この出入りの感覚をいい加減にすると、自分の命を落すことにもなりかねない。
何とも格式的だ。 この感覚は上下足の習慣にもつながっている。 何故、わざわざ士足から素足に変えるようになったのか諸説あるようだが、ともかく素足は無防備な状態であるから安全地帯を意味している。 神聖な場所が住まい。 だから玄関は一段高くなっていて、簡単には上がれない。 そのような住まいを持てるというのは地位の象徴でもある。 それなりの地位につくと家がほしくなり、玄関は自分自身の鏡になる。 まさに玄関こそ尊いところなのだ。
一方、車いすで問題になるのも玄関だ。 地位の象徴だから、多くの場合段差を無くすことなど言語道断。 それまでの自分を否定することになるから、多くの場合、激しい抵抗にあう。 車いすを使う身になることは、社会の負け犬になること。 醜くなった自身を衆目にさらすことは人生の終わりに等しい。 何もせず、入りにくい家に住めば住むほどに、本人は孤独になっていく。 誰も寄り付かず、どこにもいけなくなる。
本当に終わりだ。
そんな戦時中の神風特攻隊みたいなことを平気で考えるお年寄りがいるから驚く。 個人的には、そんな孤独な人生をおくることは願い下げだ。 格式を捨て、境目の無い、対等な関係が求められている。
多くの人との出会いの場が玄関。残りの人生を楽しくするか、孤独にしていくのか、象徴的な入り口としての「玄関」。あなた自身が決めるものだ。 すべては、あなた次第だ。
文:白木 写真:丸山
写真:いかめしいはずの玄関もファミリーコンサート場に変わる |
● 5.引き戸と開き戸 月刊「浄土」 2004.4. >>INDEX
 場所を広く、有効に使おうとする場合に多用するのが引き戸だ。 障子や襖が、それにあたる。 高さも天井まで目一杯とって部屋の共有を計れるから、多目的な用途を求める和室にはうってつけだ。
農家に見られる田の字型の間取りも発想は同じだろう。 食べて、飲んで、歌って、寝て、と用途は本当に多様だ。 結婚式から葬式まで自宅で済ませたこの国の生活に裏付けられていて興味深い。
反対に開き戸は場所を限定的にさせられる。 プライバシーの確保や防犯上も安心でき、現代人にとって馴染みが深くなってきたドアと言えそうだ。 オシャレな雰囲気をつくってくれ、インテリアとしては西洋風。 考えてみると、日本の家に畳の数が一桁になってしまい、和室が一部屋くらいしか見当たらなくなった実状を裏付けているようにも見える。 今やほとんどの日本人の暮らしが、西洋化してしまった感さえある。
出入りロで気になるのが、わずかな敷居の段差だ。もちろん引き戸の場合が圧倒的に多い。 これは日本的なすまいほど段差が目立ち段差解消が求められていると言うことか。 だからといって「開き戸」がいいかと言えば、そうとも言えない。 畳の間が板の間に変身しても、ドアは段差無しの「引き戸」に変身することは多い。 和魂洋才の一つかもしれないが、珍しいことではない。
日本人特有の「咀嚼文化」から新しい文化が生まれたようなものだ。 狭い敷地に家を建てているところが多い日本では、場所を取る「開き戸」より「引き戸」が庶民感覚としては馴染みやすい。 ただ、住みにくさを解消するため「開き戸」をモダンな「引き戸」にするくらいしか思い浮かばないとしたら何とも情けない。
「狭い」戸建ての持ち家を奨励してきた住宅政策に躍らされた庶民に罪はない。 西洋風の家づくりに憧れて自分の家を持ってはみたが、高齢化が進みすぎ、気がついたら何とも住みにくい家に様変わりというのが本音だろう。 いつも住宅政策は後手に回る事が多い。
高齢社会をひかえて、庶民としては根本的な家づくりのための制度の見直しを必要としている。 この庶民感覚と行政側のサービス意識のズレは何とかならないものかと思う。
文:白木 写真:丸山 |
● 6.バリアフリーのきっかけ その1 月刊「浄土」 >>INDEX
 「全国初バリアフリー」の文字に関係者の心が踊ったのが七年前。 そのきっかけを考えるとさらに三年はさかのぼる。 十年前からはじまった「低床電車」導入の動きは様々なことが重なって芽吹いた。 その一つが「バリアフリー」を望む市民の動きだった。
障害者グループとともに欧州の低床電車を体験するツアーを組んだのが十年前。 先進地といわれたフランスのグルノーブル市で現代的な低床電車に乗ることができ、同行した車いすの仲間は大いに盛り上がったものだ。
今まで知らなかった乗り物で、こんなに便利になるのならと思うのも当然と言える。 帰国してから「低床電車」をというキャンペーンが展開された。 「低床電車でないと乗れない」というのが掛声となった。 幸いにも熊本市交通局がこの声を背景に全国初の低床電車一両を導入。 これは少なからず待望していた全国の電車ファンを喚起するきっかけにもなったようだ。 事実、当時交通局は相次ぐ県外からの視察客の対応に追われていた。 現在まで5両が低床電車に替わった。
ここまでくれば低床電車の導入は成功したともいえるだろう。た だ導入されたことで新たな問題も生んだ。というより導入されたからこそ新たな問題が出てきたと言ったほうが正確かもしれない。
「車椅子で利用できない停留所が多いのに電車を買ってもしょうがない」、「待っても乗れる電車が来ない」など多くの声が噴出した。 もっともな声だ。だからといって「バリアフリー」ではない、「利用できないと」言うのは早計だろう。 導入されたから初めて気付かされた問題が多いからだ。
グルノーブルでは、路線までが全く新しくされたもの、走っている車両がすべて低床電車と万全を期しての導入だった。 国内の多くの都市で始まっている新型電車(低床電車)導入の動きは、これとは根本的に違っているようにみえてならない。
先日、熊本でこんなことがあった。 車いすで乗る機会があり、定刻にくるはずの低床電車を待っていた。 しかし運休とわかり次の低床電車まで一時間ほど待たされた。 次の低床電車もリフトが故障。バリアフリーの捉え方に多少のズレを感じさせられた場面だった。
こんな熊本だが、新たな動きも見えてきた。さらに沖縄にも。 次回は今後の「バリアフリー」の動きを探る。
文:白木 力
写真とコメント:丸山 力
アルクマール(ネーデルラント)の低床バス
座席配置が非対称で乗降が滑らか。バリアフリーが基本デザインを進化させた |
● 7.バリアフリーのきっかけ その2 月刊「浄土」 >>INDEX
 同様の動きが沖縄にもみられる。 沖縄市に限らず沖縄には電車の姿はない。 もちろん「ゆいレール」というモノレールが那覇空港と首里間で営業を開始した。 しかし使いやすいものではない。 そんななか、中部の沖縄市で民間の鉄道会社が誕生した。 関係者の話によれば、この会社の計画では「バリアフリー」は最も重要なテーマらしい。 新路線誕生は、簡単な事業ではないだろうが、利用者の声を聞くことで、市民の足として街の魅力アップになるだろう。 大いに期待したい。
どのように小さな路線でもいい。 バスや電車の全車両の床が低く、停留所も広く安全に乗り降りしやすければ、市民は「バリアフリー」のきっかけを、そこに感じるはずだ。 どこのまちが、先にスタートするか楽しみになってきた。 しばらくは、そんなまちのバスや電車の動きから目を離せそうにない。 |
● こんな調子でいいですか? バリアフリーデザイン研究会 2001.6.17. >>INDEX
|
0-1. こんな調子でいいですか?
バリアフリーデザイン研究会 週間コラム
来ない、乗れない、座れない。
遅い、高い,降りられない。
路線案内は分からない。
しまいにゃ怒られ、もう乗らない。
これは、何だと思いますか。もちろん、路線バスへの印象です。バス会社の人には、耳の痛い言葉だと思います。何も感じないとしたら、絶望的かも。車から公共交通を利用する機会が多くなって、日常的に、目にするようになりました。残念ですね。
特に、乗客がお年寄りのときに目を被いたくなります。運転手だけが悪いのではないことは、わかってます。心の休まらない運転手の仕事の内容からみて、つらい労働環境にも、拍車をかけています。本来の運転以外の業務、運賃の受け渡し、そして安全確認と言う責任。重圧は、運転手のこころをむしばみます。
さらに、物言わぬ乗客である多くの「市民」は、バスに乗りたくなくなるか、乗ることを減らし、快適な自家用自動車に向かいます。
地球温暖化を推進させるクルマから、温暖化を抑える公共交通に、どう向きを変えさせられるか、乗客の、こころの声に耳を傾けませんか?
結果として、バス会社の経営自体にも影響を与えることにもなるでしょう。未来は、ひとり一人の責任が果たせるかどうかで変わるでしょう。時代の転換点に、自分たちはいるようです。
白木 力
|
● ロンドンタクシー 西日本新聞掲載 2001.9.9. >>INDEX
|
0-3. ロンドンタクシー
バリアフリーデザイン研究会 白木 力(2001/09/09)西日本新聞
欧州視察の際、到着翌日の朝、駅前の歩道でタクシーを待つ私たち数名の近くに、車体の背が高いロンドンタクシーが静かに止まりました。
話には聞いていましたが、見かけは古めかしい車体で、お世辞にもカッコ良いとは言えません。
車道と歩道の段差があったので、車椅子では必要なスロープ板は使わず、車椅子の乗客はドライバーの介助で乗ることができました。
ロンドン郊外の町で拾ったこのタクシーでロンドンの中心地まで向かいました。
ロンドン市内には、このロンドンタクシーが約1万台走っているとの事。聞くところによると、低床型の乗車定員五人のこのタクシーは、車種がいくつかあり、車椅子が乗れない車種もあるそうです。
しかし、西暦二千年までにすべてが車椅子乗車が可能な車種に義務づけられるとの事で、古い車種は姿を消しそうです。
正確を期して電話で呼ぶことも可能ですが、流しのロンドンタクシーを捕まえることは難しいことではなく、通りで我々も乗車拒否に合うことなくスムーズに乗れました。
もちろんドライバーの教育は徹底していて、車椅子の乗降の際の手際の良さは素晴しく、今までのタクシーに対するイメージが変わりしました。
福岡県では、タクシーのドライバーが二級ヘルパー資格を取得して乗客のケアーまで気を配るタクシー会社「メディスケアタクシー」が登場してます。
これこそ、業界の枠に囚われないバリアフリーなサービスと言えそうです。
熊本にも、登場していますが、ご存じですか?
交通の自由化へ向けて、国内でも、ドアからドアまでのサービスで「福祉だけ」と言う枠を除いていく事業者が増えていくことを期待します。
いい時期に来ているようです。
バリアフリーデザイン研究会事務局長 白木 力
西日本新聞掲載
|
● やぁっぱ、歩道橋には注意しましょう バリアフリーデザイン研究会 2001.8.5. >>INDEX
|
先日の兵庫県明石市の花火大会での将棋倒し事故は、どう考えてもおかしい。
いくつも、なぜ?なぜ?なぜ?てのがつづきます。「あの歩道橋は、あそこに必要だったのでしょうか?」から始めないと、このなぜは終わらない気がします。
なくなったみなさんのご家族の不満は行き場がありません。
歩道橋さえなければ、
歩道橋に、人が眺望するスペースさえなければ、
歩道橋の上り口が、2ヶ所以上あったら、
歩道橋の幅が、もっと広かったら、
みんなが歩道橋にいかずにすんだら、
考えると、もっといっぱい出てきます。
歩道橋は限られた人数、限られた人のためにあるのでは。
特に足腰に問題のない人たちへは、その場所を優先し、障害を持った人たちには、とてもつかえない場所です。
まして、エレベーターがついたとしても、乗り降りの数には限りがあります。
事故現場近くの人がとった写真を見ても、確かに、限界を超えていたように見えます。
なぜ、このような高いところを作ったのでしょうか?起こるべくして起こった事故、人災だったとしか思えません。
十万人を超える催し物だとしたら、地上で迂回できる場所を、もっと多く用意できたのではないでしょうか。
亡くなられた方には、無念としか言いようはないですね。
これは、何もあのイベントでおこった事故だけに限ったことではなく、巷にあふれている横断歩道橋でも起こりうるのです。
共通して言えることと思います。
人の自由な動きを制限している横断歩道橋をなくして、地面に作る一般的な横断歩道を増やすこと。
さらには人を優先する考え方を徹底すること。
それが必要ですよね。
これ以上、無用な横断歩道橋や跨線橋は作らないようにしては。
今ある横断歩道橋、跨線橋にしてもしかり。使いにくくて、危ない歩道橋は、無用で、ムダ。
人の往来が多い市街地では、道のバリアは、クルマそのものであることを夢夢忘れないようにしたいものです。
歩道橋自体の問題点に目を向けるときに来ているように思います。
バリアフリーデザイン研究会事務局長 白木力(2001/08/05)
|
● 1.低床電車の出現 熊本日日新聞 1998.10.8. >>INDEX
 世界の都市交通を調査し、日本で低床電車や低床バスの利点を訴えてきた私にとって、熊本市交通局の低床電車導人発表(1995年12月)は喜ばしいものだった。 またそれ以上に全国では大きな反響を呼んだ
これをきっかけに東京、大阪、名古屋などの大都市がノンステップバスといわれる低床バスを我先にと導人した
「低床ブーム」だ。 しかし、導入の過程では熊本市と他都市とは大きな違いがあったことを見逃してはならないだろう
大都市の低床バスが身体障害者団体などからの要請を受けた形での受動的な導入であったのに対し、熊本市の低床電車は障害者や高齢者などの希望と交通局自体の狙いが、うまくかみあった結果と言える
つまり経営改善の手立てとしての導入であり、より能動的であった
低床電車のメリットは、安全でしかもスムーズな乗降ができることで、乗務員の負担を軽くする
大幅なスピードアップも可能で、その有利さは在来車両との価格差を補って余りある
熊本の低床電車導入は熊本市と市民が一致してそのメリットに着目したもので、限定された人たちへの配慮だけでなく、都市の発展に有効だと判断したからである
もうすぐ低床電車も3両になる。 低騒音、省エネルギー性はもとより、まだ十分生かされていないが、非常に安全に、高速で、大量輸送の可能性のある新しい道具で、地域に与える影響は計り知れない
重要なのは大都市の動きに左右されず、住民もこの電車や低床バを都市の総合的なシステムの一つとして育てていくことである
そのような都市と市民の営みが、地域の穏やかで着実な発展を進めていくことは間違いない |
● 2.熊本の交通は進んでいた 熊本日日新聞 1998.10.15. >>INDEX
 都市の多くが自動車交通量の増大に対応して路面電車の廃止、車道の拡幅、歩道橋の設置などを行ってきた
しかし、これらは歩行者や自転車にとっては迷惑なものが多かった
特に身体障害者や高齢者は歩道や歩道橋などでいらぬ苦労を強いられている
この点で熊本市の交通対策は先進的だったといえる
古くは上通・下通・新市街の歩行者専用化、スクランブル交差点の導入、路面電車の活性化、電車とバスの冷房化、一時停止不要の踏切、近くはバス終日専用帯(大抵の都市では不法駐車に占領されている)
バスの右折大曲り、会社別から方向別の案内にしたバス停、低床電車や低床バスの導入などと優れた施策がいくらでもある
また、欧州の街で見てきたのはこの20年ほどの間に欧州の街づくりのキーワードが「地下鉄・クルマ」から「路面電車・自転車・ベビーカー」に大きく変化したことだ
そんなことは分かっていると、情報として知っているだけの大都市からは、実際に運用をしている熊本の環境はうらやましく見える
そのように進んだ熊本市の環境もまだ十分ではない
設備(ハードウェア)の改良も必要で、それらが単独ではなく、連携して効果を発揮するような運用をしていく必要がある
例えば、交通センター内で横断歩道がない、バスの間隔が5分のあとは20分だったりする、低床電車に乗るために歩道橋の階段がある、などというのは運用が悪いのである
運用といえば、九州自動車道の植木・松橋間のみを無料にするというのはどうだろうか
料金は熊本市などが負担するが、市内を通過するクルマと排ガスが減って、安全な街になるならこれは安い
ばかばかしいだろうか
|
● 3.ベビーカーと電車に乗る 熊本日日新聞 1998.10.22. >>INDEX
 熊本の電車・バスで「ベビーカーは畳んで乗るべきか否か」などと議論があったと、神奈川に住む私のところまで伝わってきた。多分その主な原因は電車やバスの混雑にあるのだろう
千葉県には車内どころか駅構内でもベビーカーを畳ませる鉄道があり、批判の的になっていた。確かに、ここには「公共交通は混雑しているもの」などという大都市の理論がある
熊本電鉄の電車はベビーカーは畳まずに、それどころか、自転車を乗せることを認めている
これを首都圏で紹介しても、すぐには信用されない
しかし、座席が少なくて立ちづくめの電車やバスでは、「乗る楽しさ」はなくなってしまっている
こうなると、たとえ渋滞していてもクルマを選んでしまいそうだ
昨年熊本市の低床電車について行ったアンケートでも「座席が少ない」という意見が多かった
もっともな意見で、座席は安全のためにも増やすべきだ
車体数も増やす必要がある
熊本市電のうち比較的新しい車両は二両連結にもできる
広島市では三車体の電車が多い
熊本型の原形となったブレーメン市では倍の長さの四車体で走っている。
バスの場合も、車体を長くして座席を増やすことができる、価格は大して変らない
工夫すれば多くの乗客が座れるようになる
そうなれば、「ベビーカーは畳むかどうか」という議論そのものがなくなるだろう
ここで提案、どの電車やバスにもベビーカーを乗せるスペースを作ったらどうだろう
乗り降りには若い乗客が手を貸してくれる
そんなうれしい光景を頻繁に見るためにも、これは熊本から始めたい
大都市でないことが熊本の幸運なのだから
|
● 4.低床バス、その次のステップ 熊本日日新聞 1998.10.29. >>INDEX
 みなさんは、既に一度は低床バスに乗られたと思う
出入り口に階段がないので、乗り降りがスムーズなことを体感されただろう
近い将来には、バスの出入口と停留所の縁石との段差はほとんどなくなり
低床バスや電車の乗り降りは、エレベーターのようになるはずだ
ところで、前3回の稿で筆者はバスと電車に「低床」と付けている
行政や学者は細かく区分しているが、現実には行政でいう「超低床ノンステップ」しか「低床」の名に値しない
もちろん乗客にとっては、「低床」なのか「低床ではない」かが重要であって名前は重要ではない
低床バスと従来型のステップがあるバスとの価格差は縮まって、もうバス会社は「低床ではないバス」を市内バスとして購入する必要はなくなったといえる
「低床ブーム」は熊本の動きがきっかけになった
しかし、これは都市の交通をよりよくする第一歩でしかない
熊本は「次のステップ」に進むべきだろう
まだ手付かずの問題が待っているからである
その問題点には、乗客から見ただけでも、デザイン・低公害技術・案内のしかた・運行時間・乗り換え・運行速度・乗務員の応対・料金制度などがある
なかでも、どうしても改善したいのが「料金制度」だ
これこそが日本の都市交通をここまで悪化させてまった最大の原因である
たとえば、バス料金は近距離でも一度乗り換えると260円もかかったり、週休2日の時代に1ヶ月定期が片道料金の45倍もする
これは日本の運賃システムそのものが現実に合わなくなってしまったからだ
次回には改善が可能な例を紹介したいと思う
ただし、どの問題を改善するにしても、今後は自治体だけでなく市民の参加がどうしても必要だ
|
● 5.改札のない電車・バス 熊本日日新聞 1998.11.5. >>INDEX
|
「熊本市の交通は進んでいた」と以前に書いた。 しかし公共交通の料金システムは悪くなる一方だ
細かすぎる料金の区間がその一例だ。 小銭のやり取りとそのチェックで乗客と乗務員の負担が大きいためか、乗務員の応対がいつも問題になる
高価なプリペイドカード装置は不完全で根本的な解決にはなっていない
それどころか東京都多摩市や稲城市などでは、カード導入後にバスの遅れがひどくなってしまった。 一年を過ぎても解消されない
しかし、優れた実績をあげた料金制度もある。「ゾーン料金・自己改札」制はその代表的なものだ
これは料金の区間を大まかで簡単な「熊本東・龍田・旧市街」などの広い区間(ゾーン)に設定して、そこへはどういう経路でどう乗換えても、一定料金で行けるようにするものだ
例えば「熊本東から旧市街」の二区間では一日400円で鉄道・バス・電車に乗り放題、といった具合に
ドライバーは安全な運行に専念するために料金のチェックはせず、乗客自身にまかせる。 そうすれば、どのドアからも乗り降りができ、料金関連の機器は簡単になる
これで公共交通全体がスムーズで高速になる。 それ以上に社会的利益は大きく事業体も決して損はしない
欧州でもワンマン化以後にこの制度は各都市の公共交通を経営改善に導いた。 日本の官庁や学者はこのことをよく知っていながら実行させようとはしない。 しかし不正乗車が多いといわれる米国でさえ普及しはじめた。 日本でも実現できないわけがない。いろいろな改革をしてきた熊本の自治体や市民なら、全国にさきがけて「乗客を無視した料金制度」から「料金までもがバリアフリーな制度」に変えることが可能だと信じる |
● 7.誤解されたバリアフリーデザイン 1998.11.19. >>INDEX
 最近、ときどきバリアフリーデザインが誤解されているのではないかと感じることがある
バリアフリーデザインとは、個人のさまざまな都合によって超えられない障壁を、なるべく初めからつくらないようにするデザインである。 範囲も建築などのハードウェアから始まり、今では社会的なデザインにまで広がっている
段差にスロープを渡したようなものでは十分とはいえない。 この要件から外れる例では、エレベーターを付けた横断地下道や歩道橋がそうだ。 仙台では市長がそれを「バリアフリー都市の象徴」と自慢しているが、歩道橋そのものを撤去することが先決だろう
同じ誤解がリフト付きバスの開発と導入だった、リフトの機械的な動きに惑わされたのか、10年以上も前から国内で実用化されていた低床バスを見ようとも育てようともしなかった
バスのカードや鉄道の自動改札もそうだ。 何やら複雑なメカニズムのほうが優れたシステムのように見える。 しかし、そういう高度な装置を使わない「自己改札」のほうがバリアフリーの面でも優れている
カードといえばテレホンカードの切れ込みだ。 挿入する方向が判別でき、優れたユニバーサルデザインと米国で誉められたが、これはおかしい。 裏でも逆向きでも使えるカードや公衆電話を提供しないのは怠慢というしかない
基本的な機能を満足せず、見かけのバリアフリーに終わっているものも一部にある。 起き上がるのには便利でも寝るには不快なベッド、ハイテク素材で軽快そうだが長く座っていられない車椅子などがそうだ
誤解されたバリアフリーデザインによる「ガラクタ」で、家庭や都市が見苦しくなっているところがある。 歪(ゆがみ)は、市民の参加で改善していかなければならないと思う
|
● 8.熊本型タクシー 熊本日日新聞 1998.11.26. >>INDEX
|
「移送サービス」というボランティアがある。 リフト付きワゴンで体の不自由な人たちを送迎するなど、首都圏ではかなり早くから活躍してきた
しかしこのサービスは様々な問題を含んだまま今に至っている。 例えば車椅子の乗客が東京駅に到着したとしても、東京駅に迎えに来る移送サービスの会員になっていなければ利用できない。 しかも夜間は走れないとか、サービス地域が狭いなどの壁がある
白ナンバーだから事故の際の補償や報酬などの問題もある。 確かに実績はすばらしいが、行政がボランティアに依存した状況はよくない
一方でタクシー会社が運行する「福祉タクシー」も奮闘している。 しかし、こちらにも問題がある
やはり夜は営業できないとか、タクシー乗り場や流しで客を乗せられないなどの壁があり、利益が少なく経営者にとっては頭が痛い
ところが、今年になって福岡や熊本に「壁」に挑戦するようなタクシー会社が現れた。 つまり行政の補助なしで運転手にケア資格を取らせたり、客席シートが外に振り出すセダンを購入し、障害者も一般客も、いつでも誰でも乗せてしまおうというものだ
これなら玄関から玄関どころかベッドからベッドへの送迎や、車いすの酔客を飲み屋街で拾うことができる。 これが本来の姿だろう
こんな挑戦を応援したい。 自治体側からも支援の方法があるだろう。 車両もリフトや振り出しシート付き車両以外にもう一つ、ロンドンのタクシーのような背の高い車がほしい。 機械を使わずに低床バスのように車いすのまま乗り込めるし、一般タクシーと兼用なので、会社は車両を増やさずにすむ
熊本から提案する「熊本型タクシー」。 ぜひ実現させて全国に広がるのを見たいものだ。 |
● 9.路面電車の新路線 熊本日日新聞 1998.12.3. >>INDEX
|
交通と環境対策で成果を挙げたドイツ、フランス、デンマークなどの街には日本から調査団が頻繁に訪れる。 しかし「よく調べるが、何もしない」という評判通り、国内で満足できる「回答」を見たことがない
真に学ぶべきは「公共交通は都市の基盤。だから国や都市が公共交通に投資している」事実ではないだろうか。 投資は単なる赤字補填を意味しているわけではない
事業体だけ見て「赤字が何億」などというのは縦割り的な考え方だ。 公共交通ネットワークを、より広範囲に、質を高めるには電車の新線が効果的だし、社会全体で見ても安上がりだと思う。 建設費は1km当たり2億から10億円で、ようやく国の助成も付くようになった
これに対し、地下鉄は約300億円、モノレールは100から200億円もかかる。 新たに建設する路線は原則として車道を走らせていい
「そんなに広い道はない」といわれるかもしれないが、車道の両端を走れば(バスと軌道を共用)道路は拡幅しないですむ
熊本市圏の主な「新線候補」を挙げてみよう。 まず空港線。 体育館前で分岐して県庁、グランメッセを経由する。 代継橋架け替えと同時に辛島町から南熊本へ、もちろん田井島・中の瀬延長も可能だ。 北バイパスが完成すれば水道町から北熊本へ。さらに電鉄線を改良して、単線でも10分おきに辻久保や菊池へも可能。 これならクルマより速い
昨年のアンケート調査で要望の多かったのが、健軍から木山への延長と、日赤−大江渡鹿−大学病院−熊本駅線だった。 各線は民間と共同で運行し、沿線自治体も参加する。 またパーク・アンド・ライド停留所も備える。 電車の速度制限や道幅が狭いと建設できないなど時代遅れの制約がなくなれば、電車は快適さとスピードを乗客に、静かさと美しさを街に、モノレール並の輸送力を事業者にもたらすに違いない |
● 10.歩道の整備で商店街を賑やかに 熊本日日新聞 1998.12.10. >>INDEX
 熊本市の旧市街にはいくつかの商店街があるが、少し寂しい。 周辺人口が増えているのに買物客は中心街や大規模店へ流れている。 歩行者空間を良くすることで賑やかにならないだろうか
クルマに邪魔されずに、ゆっくり街歩きができ、ちょっと休める木陰のある歩道はどんな街にも商店街にも必要だ。 クルマの出入りために歩道を削った「欠き取り」がなく、高さの揃った平坦な歩道はお年寄りでも安心して歩ける
実際に欧州ではこれより進んで、横断歩道まで歩道の高さに揃え、クルマが速度を落とし乗り上げて通る交差点が出てきた
そこで具体的な提案だが、例えば新町商店街は交差点の信号のサイクルを短くする必要がある。明十橋通りが拡幅され、東西に分断された感が強いからだ。 上通は近代的商店街の老舗だが、並木坂側はそれほ賑やかではない。 歩行者専用でないとか、バス停や電停がないなども原因だろう。アムステルダムで一番の商店街はもっと狭く、電車・自転車・歩行者でごった返している。 この例に習い、思い切って上通に単線で低床電車を走らせるのはどうだろうか。 市電や熊本電鉄に乗り入れることもできるし、観光資源にもなる。 商店街を横に延びたデパートとみれば、この電車はエレベーターにも相当する(当然無料であろう)
辛島町分岐点から熊本駅への電車通りには昔日の賑わいがない。 そこで、呉服町までは通過車両が少ないから、クルマは電車軌道内を通し、現在の車道は緑豊かな歩道にしてしまう。 また祇園橋−田崎橋間は軌道を片側に寄せて敷設する。つまり樹木を中心に片側に電車・歩道を、反対側に車道が並ぶ。 そうすれば歩道脇にはアーケード街などでは飽きたりない個性的なテナントが集まるだろう
快適な街づくりには、質の高い歩道と自転車専用帯がどうしても必要である |
● 11.熊本駅と周辺の整備を没個性にしない 熊本日日新聞 1998.12.17. >>INDEX
 政治にもてあそばれながらも九州新幹線建設と熊本駅周辺の再開発が始まった。東京では様々な具体的計画を聞く。 ところが熊本で聞くとほとんど決まっていないという
独自の優れた計画を持たなければ、中央の図面のままに、従来の新幹線駅とその周辺でされたような没個性的な再開発になってしまいかねない
従来の新幹線は周辺に古いものを残さず、住宅地まで近代的にしてきた。 それは道を広げクルマを通りやすくすることが中心だが、コミュニティ−が分断されたら何にもならない。 クルマが通りにくく人が通りやすい道も残したい。 それが住みよい街の財産だからだ。 子僕が遊び、年寄りがベンチに腰掛ける路地を顔見知りの車がゆっくり通る、それでよいではないか
新幹線とはいえ熊本駅付近は低速で運転するので、ばかばかしく大きな高架橋や防音壁は必要ない(一度でも東北新幹綜を地上から貝上げれば、そのすごさが分る)。 やばり小ぶりにして、市街地の景観を大切にしたい。 理想的には駅も線路も半地下式にするのがよい、つまり天井のない地下鉄のようなものだ。 環境問題がほとんど解決し、駅の構造も簡単になる。 東急電鉄ではこの方式で改良工事をして好評だが、小田急は高架式にして住民の批判にさらされている
また従来の新幹線建設では乗換えと接続を不便にしてしまったが、熊本駅は初めての改善例にしたい。 新幹線ホ−ムから1分で豊肥線に、三角線から2分で電車やバスに乗り換えられるようなデザィンは可能だ。 そして駅には保育園や生鮮市場、図書館、公民館など、地域の生活に密着した設備があるほうがよい。 仕事を終えた母親が市場で買い物をし、保育園で子供を引き取ってベビーカーに乗せて列車で帰る。 そんな夕方のシ−ンが似合う駅にしてほしいと思う |
● 12.八代・川内間で在来線を運行する 熊本日日新聞 1998.12.21. >>INDEX
|
新幹線ができると並行する在来線は廃止するなど、日本はこんなパターンを操り返して大都市を肥満させ、地域を破壊してきた。 外国の超高速鉄道は、この「反面教師」に学び、地域も共に発展するよう進められてきた
実は、地域を切り捨てない方法はいくらでもある。 ひとつは在来綴との接続を密にすること。九州は民営化以来、特急と普通列車の連携がまずまずうまくいっているが、九州新幹線と在来線の関係は、さらにレべルアップする必要がある。 切り捨てなどとんでもない。 例えばプラットホームひとつとっても改良の余地がある。 両側に新幹線と在来線を止めれば、乗換えは数秒。わざわざ階段と改札を通らされる従来の新幹線は、自分で自分のスピードを殺している
さて九州新幹線で心配なのが在来線だ。 いったい八代・川内間をどうするのか。 国は明確に伝えようとしないし、地域は聞こうともしない。 開業間近に第三セクタ−にでもと言われても、地元には重荷でしかない
そこで今のうちから、この区間をハイレべルで運行する機構を準備したいと思う。 地域を賑やかにし、バリアフリ−の見本になるような鉄道に蘇らせたい。 軽量・高速の電車を30分間隔で運転し、八代−水俣間を50分程度に短縮する。 熊本市方面へ直通も可能だ。また車両の床はプラットホームと同じ高さにして高齢者、ベビーカー、車いす、自転車に便利にする.つまり、駅も車両も バリアフリーにするのだ
もちろん運賃収入だけでは採算が取れないから、環境地域振興、福祉などに力を入れて公的な支援を引き出せるようなビジネスを展開する。 障害者の就業も大歓迎だ。 夢みたいに思えるかもしれないが、十分実現可能な計画で、来年早々にも動きだしたいと思う。 計画の一部にでも参加しようという人はいないだろうか |
 電停で待たされること一時間。骨折を理由に車いすで低床電車に乗ってみたが、利用しにくさに大いに戸惑った。 低床電車が走るようになって七年を経過し、広島、岡山、鹿児島、長崎、高岡と次々に導入が進み、熊本の電車も目新しくなくなってしまった
一時間もなぜ待たされたか。 それは車両の数に原因がある。 低床電車が二割程度では、バリアフリーも完全ではない。 電停も狭く、その環境も後手にまわり始めた。 待たされた挙句、故障を理由に運休では障害者は泣き寝入りしかない。 利用しにくくなれば、市民が敬遠しはじめるのではないかと余計な心配をしてしまった。
ところが最近になり、熊本の中心部からはなれた所にターミナルを持つ私鉄が、市中心部への乗り入れを検討しており、この動きが注目されている。 乗り入れに併せ低床電車に一新する計画だ。
実現までに、時間もお金もかかり困難も予想されるが、自転車の車内への乗り入れを全国に先駆けた同社の動きは、利用者の期待を大いに満足させてくれる。 具体的なプランの検討も進んでいるようで、待望する市民も少なくないはずだ。 なかでも注目したいのは、全車両が低床になることだろう。 乗り遅れても、一時間待たされる心配はない
文:白木 力 写真:丸山 力 |
(C)2002-2015 Tram21 All rights reserved CGI-design