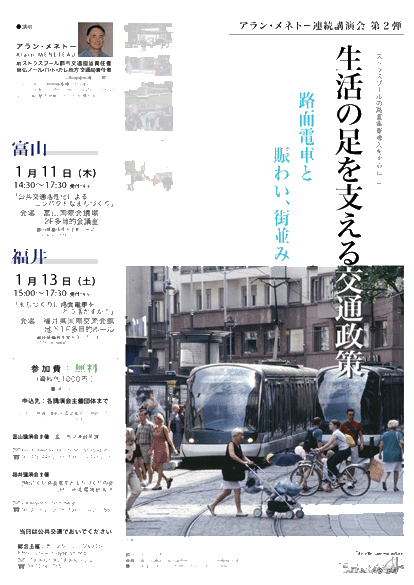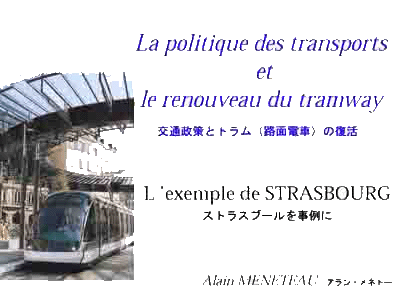INDEX ● Image appending >>image list
● 07c12 バリアフリーデザイン研究会2月例会 報告 >>INDEX
 ひとにやさしいまちづくりアドバイザー養成講座
特別公開講座ひとにやさしいまちづくりシンポジウム ソウルーくまもと
開催日時:2007年3月3日(土) 13:00~17:00
開催場所:熊本市役所本庁舎 ホール
入場者 一般120名、スタッフ23名
司会の三島春奈さんの進行で始まりました。
今回の講座で、要約筆記も用意する予定でしたが、都合で手話通訳のみとなりました。
韓国交通研究院の申さんの話の前に、ソウルの事情を少し理解していただこうとスライドストーリーを用意し会場の参加とソウルへの旅に出かけることになりました。十年ぶりに韓国を訪問する男性役を養成講座受講者の市野さん、韓国滞在中 の女性友達の役を学生の木下さんにお願いしました。
十年ぶりのソウルはすっかり変わったとの感想しきりだった金さんの印象をベースに講演に入りました。
第一部
講演「韓国における交通弱者の移動円滑化のための
法制度及び整備の現状」
講演者 申 連植 シンヨンシクさん
韓国交通研究院研究委員
韓国交通研究院で長年にわたり高齢者や障害者の移動円滑化に努力されてきた申さんは、東京都立大学大学院卒で日本語も堪能でした。
申さんの韓国全体の話から、韓国の法制度がどのような枠組みで構成されているのか、今後どのように考えられているのかなど基本的な法整備の状況などを紹介され、法整備が進んだことで、国内のバリアフリー化が加速することを言及された。
講演「ソウルにおける同法制度及び同整備の現状」
講演者 鄭 鉉靜 チョンヒョンジョンさん
ソウル市役所交通局勤務
引き続き、鄭さんがソウルの状況を中心に講演を続けられました。
鄭さんも埼玉大学大学院卒業で交通計画の専門官。
ソウル市内の移動円滑化のために尽力されました。特に、120数社あった交通事業者が事業者間の競争でしのぎを削っている状況を打開する手だてとして、バス路線改変は目を見張る内容でした。
GPSを使う運行管理するシステムの導入や、T-moneyというICカードの導入、バス専用中央走行車線の導入による定時運行への転換、停留所のデータ-ベース化と様々な取組みが紹介されました。
特に、ワールドカップで数百万の市民が集まったソウル市庁舎の画像を紹介しながら、以前の自動車主体の市庁舎前から、人が集まる人主体の広場作りが紹介されると納得という表情が会場の参加者の多くから見受けられました。
10年ほど前は、横断歩道の姿はなかったのですが、今では広場へ渡る横断歩道を見ることができます。広場の地下には商店街があるそうですが、地下へ来る市民が少なくなり売上が減ったことで亡くなったお 店の方もいたそうで、商店組合から市長へ再考の要望も出ました。市長判断で横断歩道を優先するという判断が出て、警察なども納得したということでした。
少々強権的ともいえそうですが、弱い立場の人の環境整備が進んだことは、結果としてよかったといえそうです。
第2部 パネルディスカッション
進行役 コーディネーター 鳥崎一郎さん 元ジャーナリスト
発言者 パネリスト
申連植 シン ヨンシクさん 交通研究院研究院委員
鄭鉉靜 チョン ヒョンジョンさん ソウル特別市庁交通局
裵隆昊 ぺ ユンホさん 便宜施設促進市民連帯所長
崔栄繁 さいたかのり 障害者インタ-ナショナル)日本会議
東俊裕 ひがしとしひろ 弁護士
丸山力 まるやまちから 地域デザイナー
鳥崎さんの軽妙な司会で幕を開けたパネルディスカッションは、大きく二つのテーマを問題の中心にして進められました。
「急速な変化と、それを可能にしたもの」について
申さん、鄭さんともに行政が進めている現実や今の状況を説明されました。丸山さんからも同様の指摘があり、今後の韓国の動きに多くの関係者が注目していることも付け加えられました。福祉サイドから
建設土木に所管が移ったことも補足されました。より以上の効力を発揮していくと期待されているようで した。
「まちづくりにおいて、障害当事者の人権保障をどのように実現したのか、するのか」について
ソウル在住の障害当事者の裴さんは、地下鉄駅での事故をきっかけとして障害当事者の運動が活発化していった様について指摘がありました。車両前での座り込み、鎖でレールと身体を繋ぎ鍵をかけて身体を
張った実力行使が行われた模様も報告されました。38日間にわたる断食の行使など命がけの当事者運動には、東さんも驚いた様子でした。
ソウルでは実際にどう障害当事者の声を活かしている のかとの鳥崎さんからの質問に、申さんも鄭さんもこれからの対応が重要な視点と当事者運動の重要性を認めていました。特に、移動円滑化の整備が進む施設がどう使われていくのかが今後の改善に大きな役割を果たしていくという意見は注目される意見でした。事業者が整備そのものを無駄なものだと誤った認識をしないような動きに期待しているようでした。
日本での現状は、韓国より当事者運動が進んでいるとの認識が主流ですが、東さんはハートビル法、交通バリアフリー法からバリアフリー新法へ移行し ている日本の実情を例に取りながら、乗降客五千人以上の駅を重点地区としている現行法の考え方は、小さな駅しかない地方にとっては整備が遅れることを意味し、都会は一層便利になっていき地方はいつまでも整備が進まないという、都会と地方都市という格差を助長させていくことになるとの指摘がありました。当事者が身体を張って行動しないと何も変わっていかないと強く会場へ訴えていました。韓国の動きを範として更なる当事者運動の必要性を訴えていました。また、崔さんも同様の視点で韓国の動きをじっくり見てい きたいと付け加えられました。DPI日本会議
として、今後はさらなる地域への支援が必要と強く考えられたようでした。
地方の組織強化をどう考えていくか課題を得られたようでした。
残りの時間は会場との質疑応答。興味の視点は、障害当事者の運動と行政の接点についてだったようです。申さんから、当事者が実際使うことで問題が出てくる点も認識を新たにされ、鄭さんも当事者の要望を自分たちが受ける立場にいる点について再認識している点についても言及されていました。会場にはバス事業者の参加もあった ようで、シンポジウムでの話が参考になったとの意見が出されていました。
最後に、このシンポジウムをきっかけとして両国の関係者の交流が進むことを期待して長時間にわたるシンポジウムは終了しました。
この最終的な報告は養成講座報告書で詳細に紹介します。 (文責:事務局)
写真付きの報告は、ホームページでpdfで掲載予定。別紙資料の同様です。
|
● 07a11 アラン・メネトー連続講演会第2弾 富山/福井 報告書 >>INDEX
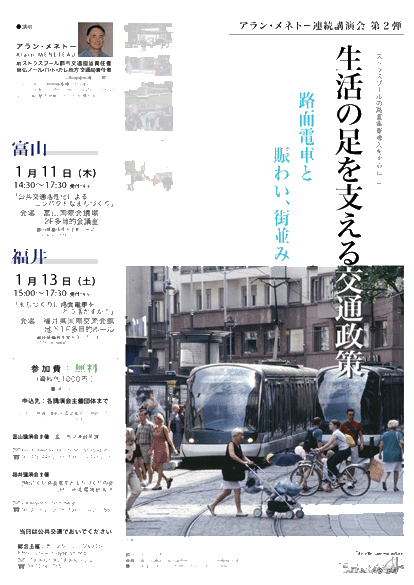 アラン・メネトー講演会
富山市による報告書
http://http.tram21.info/url_ToyamaFrm_07a.pdf
都市再生フォーラム
路面電車の活性化とコンパクトなまちづくり
- 都心地区の賑わい創出に向けて -
1.開催趣旨・概要
(1)目的
(2)開催概要
(3)プログラム
(4)講師
(5)PR
2.ガイダンス
3.基調講
4.鼎談
5.記録
------------------------------------------------
アラン・メネトー連続講演会
~生活の足を支える交通政策~
路面電車を核として街づくりを目指す富山市、福井市で講演会
講 演:アラン・メネトー:リール(仏)地方交通行政担当官
日 時:2007年1月11日(木)14:30~
会 場:富山市 富山国際会議場2階多目的会議室
日 時:2007年1月13日(土)15:00~
会 場:福井市 福井県国際交流会館地下1階多目的ホール
参加登録:各講演会主催団体までEメールもしくはファクシミリで
富山講演会:富山市交通政策課
e-mail:koutuseisaku@city.toyama.lg.jp Fax:076-443-2190
福井講演会:(特)ふくい路面電車とまちづくりの会、(財)地域環境研究所
e-mail:ire@aioros.ocn.ne.jp Fax:0776-27-7851
主催:カーフリーデージャパン
協力:日仏笹川財団
後援:経済産業省、国土交通省(予定)、フランス大使館経済部(予定)
参加費:無料(資料代1000円(希望者))
チラシのダウンロード
http://www.geocities.jp/carfreedayjapan/lib-pdf/06menetcfd.pdf |
● 07c03 ひとにやさしいまちづくり ソウル―くまもと >>INDEX
 「やさしいまちづくり ソウル―くまもと」
講演とシンポジウム
日 時 : 2007年3月3日 13:00~17:00
場 所 : 熊本市役所本庁舎14階ホール
講 演 : 申 漣植(シン ヨンシク)韓國交通研究院
演 題 : 韓国のやさしいまちづくり推進実績と
法整備状況
シンポジウムのコーディネーター
鳥崎一郎(元ジャーナリスト)
パネリスト
崔 栄繁(さい たかのり : 障害者インタ-ナショナル日本会議)
鄭 鉉靜(チョン ヒョンジョン : ソウル市役所交通局)
東 俊裕(ひがし としひろ : ヒューマンネッ卜ワーク熊本)
裵 隆昊(ペ ユンホ : 便宜施設促進市民連帯所長)
丸山 力(まるやま ちから : バリアフリーデザイン研究会)
韓國と日本の交通アクセス関係者、しょうがい当事者を交えて
主催:バリアフリーデザイン研究会/
ひとにやさしいまちづくりアドバイザー養成講座実行委員会
チラシのダウンロード 350Kb
http://http.tram21.info/b-205vi_Seoul-Kuma_trs_picc---c03.pdf
チラシ高画質 1.8Mb
http://http.tram21.info/b-205vi_Seoul-Kuma_trs---semp.pdf
開催趣旨
1999年以前のソウルの街と交通のありさまは、「これでは熊本がまだ一歩くらい先かもしれない」といえるほど厳しいものでした
地下鉄へのエレベーターはなく、車いすやベビーカーを見かけることもほとんどなかったのです
ところが近年になって、急に街の環境が整備されてきて「やさしいまちづくりが進んでいる」といわれている大阪市圏をも追い越しているのではないか、と感じられるほど際立った変化が見られるようになりました
たとえば、経路や運行会社や乗換えを問わない鉄道・バスの料金制度が始まりました
この制度は欧州ではあたりまえで、「先進国で実施していないのは日本と韓國だけ」といわれてきただけに、いよいよ目が離せなくなったといえるでしょう
また、10車線の通りにまで横断歩道を描き、地上で横断できるようになりました
このままでは交通のバリアフリーについても環境についても、日本は「発展途上国」どころか「後進国」になってしまいそうです
今回のシンポジウムでは、これまで伝えられる機会の少なかった隣国韓國での変化を紹介して、どのように街の環境やバリアフリーの整備が進められ、どのように新しい料金制度などのしくみがとりいれられたのか知ろうと思います
また、同じアジアに住むしょうがい者の視点から「やさしいまちづくり」を考えることで、当事者の権利や制度を作っていく上での問題を共有する機会になることを期待しています (まるやま ちから)
|
● 06b28 バリアフリーデザイン研究会2月例会報告 ソウル訪問記録 >>INDEX
 場所:くまもと県民交流館パレア 9階 会議室3
参加者:14名
ソウルバリアフリー調査ツアー報告
丸山力、白木力、田中節子
目的
1999年にバリアフリーデザイン研究会の森重康彦・白木 力・丸山 力により実施された「ソウルバリアフリーサーベーランス」の報告を受けて、韓国交通研究院の權 寧仁Kwon YoungIn博士のコーディネートによりソウルでの視察が可能となった。
また今回は韓国生活を長く経験された日本語教師の田中節子さん(熊本在住)の訪韓にも日程が合い、現地での通訳をお願いすることができた。
前回のバリアフリーデザイン研究会による視察当時との比較を含め、ソウルで進められている事業の数々を視察した。
結果
熊本市での事業にも生かせる多くの発見をすることができた。
以下その概要である。
ツアー参加者について
バリアフリーデザイン研究会:
白木力、村上博、井上隆一、小椋清市、小椋静子、丸山力
韓国語通訳兼現地でのインストラクター:田中節子
行程
2005.11.3.
JR九州「有明」 熊本 ⇒ 博多
「BEETLE」 博多 ⇒ 釜山
ワゴンタクシー釜山港 ⇒ 釜山駅
韓国高速鉄道「KTX22」 釜山 ⇒ ソウル
地下鉄 ソウル駅→三角地→ノクサピョン
2005.11.4.
ホテルから空港バス→仁川国際空港
バリアフリー化された空港施設視察
仁川国際空港→ソウル市庁舎
ソウル市庁舎 都市交通局
清渓川復元事業現場
交通システム改良
2005.11.5.
ホテルからワゴンタクシーでソウル駅
「KTX81」 ソウル ⇒ 釜山
「BEETLE」 釜山 ⇒ 博多
市内バス 博多港→博多駅
JR九州「有明」 博多駅 ⇒ 熊本駅
今回のツアーは、個人的な内容に終始しましたが、ソウル市内での情報交換については韓国交通研究院の研究員の方へ全面的な協力をえて実現しました。
現地関係者の皆さんへ感謝を申し上げます。
視察メモ
2005.11.3. ソウルまで
高速船ビートルにて韓国。
乗船においてのバリアフリー体験。
釜山港は、アジア、日本との共通したものが見受けられる。
上下船のバリアフリーは現状では人手が要る。
入国管理を抜け、港のターミナルビルを出ると、入り口近くで口論中の夫婦に遭遇。その韓國語の激しいやり取りに、初っ端から韓国ショックを受けてしまった。
釜山駅。APEC前ということもあり、警護の警備員に国内の緊張を垣間見た。
街中の雑然とした風景は伊湖を感じさせないが、対照的な改装された釜山駅の現代的な駅舎はあまりにまぶしい。
広場からエスカレーターで駅舎内へ。村上さんの車いすを目ざとく見つけた駅スタッフが、構内までサポート。なぜかタスキをかけていて選挙風景を連想さえた。足腰が少し不自由な井上さんにも車いすを手配してもらう。いかにも介護用のものとわかるデカイ車いすのタイヤには、空気が入っておらず、ベタッとひしゃげたタイヤが気になって仕方がなかった。
韓國高速鐵道KTXの客車は2号車に障害者用席がある。日本の駅と違い、ホームが低いため乗降用のキャスター付きランプが必要。それをKTXの乗降口に設置した男性乗務員は突然、ランプの上で2、3度ジャンプした。村上さんの方を向いて、「大丈夫!」と言わんばかりの得意げな表情に何かほほえましさを感じた。その男性スタッフと更に女性スタッフも加わり、金具付きのベルトを持ち出し車いすを固定し始めた。
しかし、不慣れなせいか、固定に時間がかかった。できあがるとベルトの張り具合を確かめながら、例の大丈夫と言った得意げな表情。そんな乗務員の行動が気になる一方で、移動が不自由な井上さんを介助するでもなく、井上さんは一人で座席に移動していた。
相変わらず乗務員は、村上さんが乗ってない空の車いすを固定するという状況。
車いすの利用者が、まだ極端に少ないからか、汗だくの乗務員の様子に初々しさを感じた。
KTXは無事に定刻にこれも改装なったソウル駅に到着。到着ホームでは釜山と同様に、仮設スロープで下車。エレベーターで2階に上がると、そこが待合のホールとなっていた。田中節子さん(通訳兼現地インストラクター)とはその出口で合流。ソウル駅を後にした。
流暢な韓国語を操る田中さんに、参加者もほっとひと安心した様子。地下鉄を利用しようという案で、思いがけぬ距離を歩くことになった。井上さんが遅れて移動。少々気を使うことになった。
地下鉄ソウル駅→三角地→ノクサピョン(ホテルの近所)。
地下鉄の乗り継ぎやホームは、はっきり言ってわかりづらく移動の不安は感じられた。右往左往という表現がピッタリ。構内は、どういうわけか日本区内の地下鉄の様子を連想させてくれる光景だった。文字はハングルと小さな英語ではあったが。やっとの思いで到着したホテル近くの地下鉄駅から地上に出ると歩道は予想以上のでこぼこ。勾配もあり、ホテルまでの道のりが遠く感じられた。
ホテルにてチェックイン後、再び繁華街で食事した。ホテルにはKwonさんからファックスが届いていた。連絡を入れ、翌日の約束を確認した。Kwonさんも予定よりは多少時間がとれるとのことだった。
夕食はすべて、田中さんにお任せした。韓国ならではの料理を堪能することができた。
(追記)
地上からソウルへ行くというのは、通常では考えられないツアーです。時間と費用が、飛行機で行くより割高感があります。ビートルは高速船なので揺れないかというと、港では予想以上
に揺れを感じました。船酔いを心配される方は、飛行機でソウル入りされることを勧めます。
ちなみに熊本からソウルへは、「アシアナ航空」が乗り入れしています。パックのツアーであれば格段に安くなります。
あくまで、バリアフリーの体験ツアーが大きな目的でした。
思わぬ困難にも出くわし、9時間ほどの移動を余儀なくされました。疲れる旅であったことは否めません。
2005.11.4.
クラウンホテル→仁川国際空港へのリムジンバス
仁川国際空港にて>
空港で10時に待ち合わせていた韓国交通研究院シン・ヨンシクさん(現:首都大学で博士取得)は、来韓した東京大学と運輸政策研究所の先生方の接待で時間を取ってしまい、合流まで30分待つこととなった。その間にメンバーは自由行動、トイレや店舗などを散策しバリアフリーチェック。いくつか気になった点が見つかった。
ちなみに、これまで日本からは中部国際空港建設で関係者がたびたび視察に訪れたと聞くことができた。その成果が同空港にも生かされたはず。
シンさんと一緒にきていた助手のキム・ヘジャさんが所属するのはKOTI(韓國交通研究院広域都市交通室)。実に丁寧に限られた時間で空港内の所要個所を案内していただいた。さらに、もうひとりのキムさん、キム・ヨンウさんは仁川国際空港旅客広報業務担当。同上のボランティアのおじさんもキムさん。キムさんは多いのだ。このボランティアのキムさんは、空港案内の仕事に誇りを持つ気のいいおじさんだった。もちろん空港事務所のキムさんも、空港のバリアフリー化には誇らしげにしていた。
「近くの熊本に居て、なぜこの空港に初めてなのですか?」と興味ありそうな質問もあった。今回熊本から地上ルートで訪韓したことも非常に興味ありそうだった。
仁川国際空港は、別紙資料でもわかるように、将来世界一のハブ空港になる計画が進められていて、現在は世界3位とのこと。2020年に終了する第4期工事まで、アジアの拠点空港でありつづけることは、熊本市にとっても大いに利のあることかもしれないと思った。
それ以上に、現地空港関係者にとって日本からの視察ツアーが途切れないのは、うれしい悲鳴のようにも聞こえてしまった。
空港内で案内を受けたエレベーターの設置状況、使い勝手、基本的な要素は負けていない。オーチスエレベーターが管理しているようで大きな問題はないようだった。各国、各民族といった多くの人たちの使い勝手に叶うものかはこれから試練を受けるのだろう。限られた時間で、全てを云々することはできない。しかし、この空港の力の入れようは、空港パンフレットやインターネットでの海外へのサービスを見れば、至らない部分は改良していくという姿勢に、それを証明しているといっても過言ではない。
今回の仁川空港訪問は、地上からのアクセスだったが、次回は熊本空港から入港することで、空の玄関としてのバリアフリーの状況がより把握できるものと確信した。
空港レストランにて食事
シンさん、キムさん、来訪組7名にて、韓国料理で昼食。飲食店のバリアフリーの状況や対応を実感。食事後に移動する中で、空港内の要所要所にエレベーターが設置してあり、確かに積極的と感じられた。
余談
コーヒータイムに村上さんから「だれがこのバリアフリー化にゴーサインを出したのですか?」との質問に。シンさんからの説明でも歯切れの悪さを感じた。とても説明するのに苦労しているようだった。
「世界一流の都市ソウルを目指している状況も後押ししているようだ」というのが説明として聞こえてきそうだった。今や韓国内バリアフリー化にShinさんはなくてはならない存在。
バリアフリー化、ユニバーサルデザインへの大家として、重い責任が求められているように感じた。6年前からすれば、近代化に伴う国内のバリアフリー化は、最重要課題のようで、情勢は以前に比べ予想をはるかに越えて一変していた。
このような一連の専門的な会話にも、田中さんは韓国語で巧みに通訳を果たされ、熊本グループのわがままな問いかけにも臆する様子もなく、質問する側ももどかしさを感じないですんだ。
やり取りから感じた結論としては、度重なる国の議会でのやりとりも経て、難産の末にバリアフリー化が現実のものとなっ様子が理解できた。これからは具体的に実現に向けてお金や政策や人が結果を残していくより他はないのだろう。
ソウル特別市庁にて
仁川国際空港→市庁舎前まで空港リムジンバスで移動。
ソウル市都市交通局を訪問した。
クォン・ヨンインさん KOTI(韓國交通研究院 道路交通研究室 東京工業大学にて博士取得)
チョン・ヒュンジュンさん ソウル特別市都市交通局担当者 埼玉大学に留学。
空港出発が遅れてしまい、会議は1時間遅れた。到着した市庁舎前広場も一変していた。無味乾燥な道路しか見当たらなかった以前のソウルの状況から、緑あふれる公園がそこにはあった。
大幅な事業転換がなされたことを感じた。
本当に6年前には見かけなかった横断歩道。またその歩道につながって日本によくある誘導タイル、警告タイルが溢れていた。どうしたことか。変わり始めていると聞いてはいたが、このような変化には目を見張った。
市庁舎でお待たせしたクォンさんも、後の予定がありそうで、数十分の会見となってしまった。再会に握手をしたが名残惜しいものとなってしまった。「チョンさんが、皆さんの分野が担当で詳しいので、彼にお任せしました」流暢な日本語で相変わらずの清々しい表情にほっとした。 市役所担当のチョンさんの説明中も気もそぞろという感じだった。大変申し訳ないことをしたと、別れ際に再度お詫びを申し上げた。
ソウルの都市交通、特にバスの運行について
以前はソウルのバスは79社の民間会社が運行していたが、現在は自律調停機構で運行管理。運行台数と距離による実績で収益を保障する方法に改編されている。
以前の乗客数で決まっていた収入構造は大きく変わったという。車体は青、緑、黄、赤の単色
に塗り分けられて走っている。
「路線運行権」を公開入札で選定する「路線入札制」に変更され、各社しのぎを削って運行していたため荒っぽい運転やサービスの悪さは評判だった。そのことも原因し事故も多発していたという。
このシステム改編により、事故件数は減少方向に向かっている。
低床バスの普及状況は、総数8000台のうち、現在92台とのこと。連接バスも普及しており意気込みが感じられた。今後の目標として、普及率100%を目標としているようではないようなのが、少々残念。ぜひとも完全なバリアフリー化を目指して、低床バスの普及を期待したい。
市庁舎前にて低床バスを待つが低床バスには乗れなかった。復元事業のチョンゲチョン(清渓川)周辺を散策後、ファイナンシャルセンター周辺のビルの谷間びある庶民的な居酒屋で夕食。野菜中心の料理で、豚足、ワカメ、腸詰など趣向の変った品は韓国の庶民の料理と聞く。田中さんの好みの場所のようだった。「いつもくるのよ」と楽しそうだった。
食後はチョンゲチョンをさらにぶらぶら歩きながら散策。溢れかえる庶民の様子に韓国の活力をまたしても感じた。夕食後のコーヒータイム、いいひと時を送ることが出来た。
それにしても現在のソウル市長は大変な人気のようで大統領候補にという声も囁かれ、韓国内にとどまらず世界的にも注目されているようである。
いくつも事業を掲げていて、「清渓川復元工事」と「交通システムの改編」この2点は大きな公約だったとのことで、実現に向かうソウルで政策実現の息吹がいかに国民にまで意識を転換させるかを実感させるようだ。
反対派も着々と進んでいる状況には、その手腕をあらためて見直しているとのこと。ここ数年、ソウルから目が離せなくなってしまった。
ホテルへはタクシーにて移動した。もちろんワゴンタクシーで車椅子を積み込み移動した。
2005.11.5.
イテウォンクラウンホテルをチェックアウト
0830 ワゴンタクシーにてソウル駅
KTX乗車口にて、井上さんを見失った。
まだ少し残る半身の不随で、不自由な体ながらメンバーの動きにあわせていただいていたのだが、発車時間になりホームから見失ってしまった。この列車に乗る人しかホームにいないので、ホームに残っていなければ乗っているはずとの丸山さんの判断もあり、全員乗車。
KTXは発車した。まだホームに残っているはずの田中さんに連絡をとるため乗務員に携帯電話を借りた。快く携帯電話を貸してくれ、田中さんとも連絡が取れたがホームにはいなかったとのこと。
車内を移動しながら見つける。車両は18両で日本の16両より多い。最後の車両で腰掛けていた井上さんを発見。一安心した。
車椅子対応の車両へと移動を促し自分の席に戻る。途中、乗務員に携帯電話を返却。とても助かった。
往路と同様に、ビートルにて乗船。釜山港から博多港まで向かった。
入国も同様に心配したほどの事故もなく、無事に入国できた。しかし、出入国審査があることで、近くても韓国は異国とに自覚を明確に持てた。
その首都ソウルは、予想以上の大都市へと変貌している。今回のツアーを通して、イ・ミョンバク市長が市長選で掲げた公約を、夢ではなく実現可能なプログラムとして、着々と世界へ飛躍する様を見る機会を得ることができた。ソウル市民も同様の感覚として捉えているのではないだろうか。
今回のツアーでお世話になった多くの関係者に経緯と謝意を表したい。
ソウルの更なる発展を期待しながら。
おわりに
公約を実現するという政治家の手腕が、この後どのように評価されるのかも興味がある。しかし、活力のある「温かいソウル」に生まれ変わる様を再度ソウルを訪問することで、実感したいものである。
ビジョンソウル2006について
今回市役所で、ソウルの大転換を聞くことになった。イ・ミョンバク市長が掲げた「ビジョンソウル2006」これが全てだった。市長選で掲げたいくつもの事業公約の中で、とりわけ3つの事業が特筆される。
●「チョンゲチョン(清渓川)復元事業」
●「交通システムの改編」
●「デジタルメディアシティー開発事業」がそれにあたる。
中でも全世界から注目された、されているのが、「チョンゲチョン(清渓川)復元事業」だった。この復元事業の先には、21世紀の文化環境都市ソウルの実現が目標にあるという。歴史的な文化遺産が、疲弊した近代化の中で埋没しかけたときに、困難との声が多く反対もあった事業を短期間で達成していくありようは、土木計画の分野でも、「都市整備の韓流」と囃され、実現化していったソウルの活力に敬意を表して都市管理への新たなパラダイム構築に熱いまなざしが向けられている。
2003年7月にスタートした復元事業は、2006年9月に完成する。2年余りでの完成という考えられない事業実現は、異例といえるのではないだろうか。その実現を今年で向かえるソウルへ、大胆かつスピーディーに転換した、イ・ミョンバク市長の手腕は、各国の首長からも同様の目が向けられているところである。
2006年の秋に終了するこの事業後のソウルの動きは大いに注目される。
また、今回目的としたバリアフリー化も含めて「交通システムの改編」に沸くソウルの動向も視察の目玉となった。低床バスの数が急激に増えているとのうわさも気になるところであった。
数については、今後の動きを見ないと結論は出せないが「交通システムの改編」は目を見張った。
2005年7月にはUITP(国際公共交通連合)から「優秀政策認証賞」を受賞しており、市長の掲げる政策が傑出したものとして世界的にも評価された。今年6月にはUITPアジアパシフィック都市交通世界会議と展示会が開催される予定だ。
将来へ向けては
●衛星を活用した運行管理システムBMSの都市圏への拡大
●ICチップを使ったスマートカードの導入
●バス運行の定時運行を確立するための中央専用通行帯走行の拡大
●停留所のデータ-ベース化
先取りした交通システム改編へのさらなる挑戦は、他都市にも十分参考になる要素と感じられた。
短時間に成長を遂げたソウルは、副産物も抱えている。部分的に成果が見え始めた政策については、産業、経済、文化、環境、情報通信、交通、防災、福祉など多岐にわたり、大まかな内容については「みずほ情報総研株式会社のレポート」(別紙)に詳しく報告されている。ご覧いただきたい。
新国際空港はハブ空港、仁川国際空港について
Kansai International Airport Land Developmentから転載
韓国の新しい空港は、仁川国際空港、略してIIAと呼ばれている。朝鮮半島の中央、北東アジアの中心に位置。この重要な地域にあるIIAは、北東アジア地域のハブ空港として、商品や情報の交流の場として理想的な場所として計画されている。以前、ソウルには金浦空港があったが、1990年代末には能力の限界に達するという理由で、大都市近郊に新しい空港の計画が進められた。結果、空港の位置は1990年に選択され、1991年にマスタープランが作成された。
仁川国際空港建設の起工式が行われたのが1992年11月。北側及び南側の堤防の建設が終わったのが1994年。旅客ターミナルの建設は1996年に始まり、第1滑走路が1999年の11月に完成している。
基本的な空港施設については2001年3月29日に開港した。開港以来、46の航空会社が仁川国際空港に乗り入れ、金浦空港の時に比べ11上回る。仁川から世界102都市(アジア64、北米:17、ヨーロッパ15、南太平洋地域:5、アフリカ対1)に向けて飛行機が離発着。
1日平均5万5千人の旅客、4,961tの貨物があり、そして5万2千の車両が行き来している。
空港建設は4期に分けられている。第1期は1992年に始まり、最後の第4期が完成するのが2020年。第1期の完成に伴い、新しい空港では年間2,700万人の旅客、270万tの貨物、24万回の離着陸が可能ということだった。
2020年には、旅客数が1億人、貨物が700万t、年間53万回のフライトの能力を持つことになり、世界最大規模のハブ空港になると、関係者も説明に熱が入っていた。
新空港は、ソウル市の中心部から52kmのところに位置し、仁川市からは15kmのところにある。車ではソウルの中心部から40Kmの空港高速道路を使い、約50分で到着可能。KTX新線もまもなく完成する
バリアフリーデザイン研究会
事務局長 白木 力(記録文責)
清渓川の関連記事は次項に
|
● 06b23 バリアフリーデザイン研究会 会報 1月 >>INDEX
 バリアフリーデザイン研究会事務局から
2月例会の案内
バリアフリーデザイン研究会 事務局
〒861-8028 熊本市新南部2丁目1-110
TEL096-382-7881 FAX096-382-7896
ご案内
1月の例会では、バリアフリーマップ作りの取り組みの状況を具体的に説明することができました。
参加者は少なかったのですが、興味深い内容だったと参加者からは聞き、可能であれば今後の調査への参加もお願いしました。
ところで、今月は昨年の11月に実施しました「ソウルバリアフリーツアー」の報告をする予定です。
日本以上に動きに息吹が感じられる国柄と感じているのですが、今回は、博多-釜山間をつなぐ高速船ビートルで船と鉄道でソウル行きを決行しました。
また開通なった韓国高速鉄道KTXを使い釜山からソウルまで移動し、躍動するソウルでのバリアフリー調査を実施しました。
興味深い報告が聞かれることと思います。ご期待ください。
今月の例会にも、多くの皆様の参加を期待しています。
2006年2月例会
日 時:2006年2月28日(火)18:30~20:30
場 所:鶴屋東館9階 くまもと県民交流館「パレア」会議室3
熊本市手取本町8-9 電話096-355-4300
参加費:500円
内 容:1韓国バリアフリー調査報告
● 韓国高速鉄道のバリアフリー状況
● ソウルのバリアフリー化状況
● インチョン(仁川)国際空港のバリアフリーの状況
韓国調査団一行 バリアフリーデザイン研究会参加者
2その他 事務局から
*****************************
2006年1月バリアフリーデザイン研究会例会
日時 2006年1月17日 18:30~20:30
場所 くまもと県民交流館パレア 会議室3
参加者 13人
(仮称)バリアフリー地理情報共有システムの
研究プロジェクトについて
バリアフリーデザイン研究会事務局から概要の説明
(1) はじめに
今回の情報共有システムが建築研究所の中でどのように課題
として位置づけられているか。独立行政法人建築研究所から求
められている内容と目的について概要を説明
目的と内容:
1)熊本地域のバリア、バリアフリーの状況を
地図上に掲載していくシステム構築
2)地域の選定:電停周辺、中心市街地、施設、
メイン通り、郊外施設
3)バリアのある状況
4)バリアフリー化された状況
5)利用者サイドの運用の検討、アクセスの仕方、
見やすさ、利用ツール
6)その他
(2)コアスタッフ:
バリアフリーデザイン研究会 4名
システムエンジニア
九州看護福祉大学生
ヒューマンネットワーク熊本
独立行政法人建築研究所
行政関係者(予定)
利用者(予定)
関係民間団体(予定)
1. 検討体制の組織化
バリアフリーデザイン研究会は実際の調査検討今後は、熊本県、熊本市の関係部署と連携予定熊本県担当部署熊本市担当部署以上の関係者が集うことを目標にバリ研とヒューマンネッ卜ワーク熊本が中心に動く
2.運営
3. フィールド選定
熊本市内(市街地を中心にした中心部
市電各電停、
新熊本駅周辺
上熊本駅周辺
健軍商店街
水前寺公園等
4. 今後はコンテンツ内容の整理検討
サーバーの構成について検討していく
コンテンツ内容の整理
各ページのデザイン
5. 実際のデータの目標収集調査数
6. 情報提供の手法
7. 報告書の作成
(3)・他の自治体等が持っているバリアフリーマップの例
・熊本の地図
・過去の報告書、論文
(4)参考サイト
以下については、各種検索エンジンにて検索可能である。
参考になる他のサイトがあれば、事務局にも連絡いただきたい。
熊本県
城下町やまがた探検地図
http://www.kankou.yamagata.yamagata.jp/tankentai/
現在までの現地調査の結果報告>バリアフリーデザイン研究会会長
西島研究室の研究生による卒論に今回のテーマの一部が取り上げ
られ、電停を中心に周辺施設まで広げた調査結果の報告でした.具
体的な提案などは、まだ残されている状況です。
学生の現地調査で判明した、携帯の操作方法などについても利用
しやすさの点について、検討の余地が残りました。今後は、結果か
ら、新たな送信方法の見直しや調査地区の選定、調査項目の整理な
ど、次回の現地調査までに、対策が必要な部分として、目的の明確
化、将来性、調査員へ同のように動機付けするのかなどいくつかの
要素が見つかりました。対策を考えたいと思います。
このサーバーの利用イメージとしては、
●県外者が熊本に新幹線や、飛行機を利用して熊本入りを予定しているとき利用が予想。
●県内者、あるいは周辺居住者が熊本の特定の地域にアクセスするときに利用が予想。
●その時点で事前に何を調べるのか?どのような手順で調べるのでしょうか?
●基本的な動機を満たすものは何か?行きたいと思わせる内容とは
●その際に検索する項目は何か? 観光スポット、危険情報、
安心情報、公的施設情報など
以上がサーバーを構築する際に、
利用者の視点として最低限必要でしょう。
旅行客として熊本入りした県外者は、大きな荷物を持って、タクシーでホテルなど宿泊施設へ移動し、宿泊先で様々な情報を得ようとするでしょう。これが一番予測可能な行動と予想できます。
周辺地区に居住する人だったら、どのような行動をするでしょうか?
障害を持った人は、バリアフリー情報、公共交通機関情報、駐車場情報、待ち歩き情報など
どこまで用意できるのか、段階的にどう構築していくのかが、今後解決しなければならない項目。
必要な道具:携帯の機能>
システムエンジニアの橋本浩一
画像を送信できる携帯をもつことで、三世代、四世代目の携帯を使った、サーバー上への転送の手法について説明がありました。
残念ながら携帯をお持ちの皆様が全員参加できる状況にないという現実もあわせて指摘しておく必要があるかと思います。
現在はNTTドコモを所有しているユーザーが年配者には多く、若年層で、人気のあるKDDIauやDAPHONと多少利用形態が違うという現状と世代のギャップが普及の鍵となりそうです。
このシステムを使うと、画像とGPS情報をあわせて送信することで、バリアを感じる場所やバリアフリー化された場所をサーバー上に問題点や注目する点などを記載し、送ることができます。
その情報の集積から、ゆくゆくは、県内外のニーズにあわせたバリア情報の提供、バリアフリー情報の提供モバイル上で運用することができるようになります。
可能性>
このマップを使ったサイトは、利用者へ様々な情報を併せて提供することも可能で、その足がかりとなる実践研究といえるでしょう。
興味ある多くの会員の皆様は、利用者の視点でこのプロジェクトに参加可能です。
今後残り2年間ありますが、このサイトを上手く活用し、県内の多くの関係団体と連携した新たなネットワークをつくる方向で前向きに進めていきたいと考えています。
会員の皆さんのご参加ご協力を重ねてお願い申し上げます。
(記録責任者:事務局)
|
● 05o22 アラン・メネトー講演会の記録 >>INDEX
(C)2002-2015 Tram21 All rights reserved CGI-design